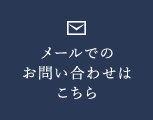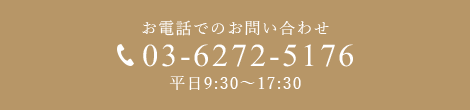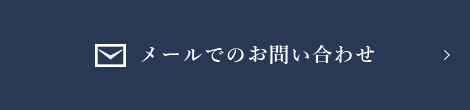一般企業顧問・試用顧問プラン
労務問題・問題社員対応(会社側)
遅刻・欠勤、メンタル不調、解雇問題を会社側で適正に整理
遅刻・欠勤が多い、メンタル不調者の復職・配置転換、能力不足社員への退職勧奨など、現場の心理分析や面談のノウハウを活かして、円滑かつ法的に適正な対応を進めます。労働審判・ユニオン交渉にも豊富な実績があり、医療・介護現場など特有のトラブルにも対応可能です。
【Q&A】1)労務問題・問題社員対応(会社側)
Q:当社の従業員で、遅刻・欠勤が繰り返される社員がいます。
さらに、メンタル不調を理由に勤務態度が不安定です。どのように対応すればよいでしょうか?
A: 本件は、「能力不足やメンタル不調による勤務不良」が重なる典型例です。当事務所では、以下の流れで対応を整理しています。
1. 事実確認と面談の実施(心理分析も活用)
遅刻・欠勤の状況を勤怠記録など客観的証拠で整理します。 メンタル不調の申告があれば、産業医面談やカウンセリングを組み合わせ、社員の主張を一方的に鵜呑みにせず、医療意見を踏まえて対応方針を検討します。
2. 配置転換や業務軽減の検討
就業規則に基づき、適切な配置転換・業務軽減が可能か検討します。 勤務環境の調整だけでなく、再発防止策として面談記録を残し、改善計画を提示します。
3. 是正勧告・退職勧奨までのステップ
改善が見込めない場合は、指導書・注意書を交付し、段階を踏んで懲戒手続きまたは退職勧奨へと進めます。 労働審判・ユニオン(組合)交渉が生じた場合も、会社側の正当性を立証できる準備を行います。
4. 医療・福祉・介護の現場特有の留意点
医療・福祉施設では、勤務態度不良が他スタッフや利用者に与える影響が大きく、早期の是正が不可欠です。 当事務所は、現場対応を熟知した上で、職場秩序を守りながらトラブルを最小化する方法をお手伝いします。
ポイント
「心理分析や外部専門家の活用」で経営者の負担を軽減
注意指導から退職勧奨まで、一貫して会社側の立場でサポート
必要に応じて訴訟対応・労働審判・組合交渉も一気通貫
【試用顧問プラン】の活用例
こうした繰り返し発生する労務問題を 社内にノウハウとして蓄積 できるよう、「1ヶ月トライアル顧問」で貴社の就業規則や指導フローを見直すことをおすすめします。
ハラスメント調査・委員会対応(会社側)
職場のハラスメントを外部窓口で早期解決
パワハラ・セクハラなどの相談窓口の外部委託、第三者委員としての調査実績も多数。小売店・工場での現場対応、調査報告書の作成、就業規則・懲戒規程の見直しまで一貫してサポートします。
【Q&A】2)ハラスメント調査・委員会対応(会社側)
Q:当社の小売り店舗でのパワハラ・セクハラの相談が寄せられました。
社内で対応すると感情的になりそうで、外部に頼みたいのですが、どのように進めるのが良いですか?
A: 本件は、「内部通報の初期対応から調査、是正措置まで」を外部専門家が一括で支える事例です。当事務所では、以下のステップを基本としています。(場合により、心理専門家、社会保険労務士等と共同で対応します)
1. 外部窓口・第三者委員の活用で冷静な初期対応
社内での人間関係に左右されないよう、外部の弁護士窓口を設置します。 通報受付からヒアリングまでは第三者性を担保し、関係者の心理的抵抗を減らすことで、事実把握が進みやすくなります。
2. 小売店・工場など現場対応の経験が豊富
店舗や工場では、上司と部下の関係が密接で 社内だけでは調査が進みにくいケースが多いです。 当事務所は現場への立ち入りヒアリング、証拠収集、関係者へのフォローまで、調査から報告書作成まで一括対応します。
3. 就業規則・懲戒規程の見直しまで一貫サポート
調査の結果、懲戒処分が必要と判断された場合、規程に基づいた手続きで対応できるかが問われます。 必要に応じて就業規則やハラスメント規程を改訂し、再発防止策として研修や窓口体制の整備までサポートします。
ポイント
✅「外部窓口+社内委員会」で従業員の納得度を高める
✅ 社内に調査ノウハウがなくても、一括で安心
✅ 店舗・工場など地域ごとの特性を踏まえた柔軟な対応が可能
【試用顧問プラン】の活用例
初めて外部窓口や調査委員を検討する企業様には、「1ヶ月トライアル顧問」で規程の現状診断と相談体制のテスト導入をおすすめします。
組織運営・内部統制の強化
AI活用・情報漏えい対策など社内ルールを最適化
社員の生成AI・ChatGPT利用に伴う情報漏えい防止、内部通報制度の設計・外部窓口の設置支援、個人情報保護体制の整備など、上場企業監査役経験を活かして内部統制を強化します。
【Q&A】3)組織運営・内部統制の強化
Q:社員が業務で生成AIを使っていますが、 機密情報の漏えいが心配です。内部統制として何から整備すれば良いでしょうか?
A: 本件は、 生成AIや外部クラウドツールの社内利用ルールを「形だけでなく運用可能な形」にする という視点がポイントです。
1.生成AI利用のガイドライン策定
まずは、どの情報を外部AIに入力してよいか、逆に「絶対に入力してはいけない機密情報」は何かを明確にします。 社員が無意識に顧客データを入力してしまうリスクを防ぐため、業務マニュアルと連動した実効性あるルールに落とし込む必要があります。
2. 内部通報制度(外部窓口)の設置
社内でルール違反や不適切な情報共有が発生した場合、早期に把握し是正する仕組みが不可欠です。 当事務所では、弁護士が「外部窓口」として対応し、社内関係者では把握しにくい通報をスムーズに受け付ける体制を整えます。
3. 個人情報保護体制の点検と改善
Pマーク取得や取引先監査でのチェック項目として、「AI活用時の情報管理」は最近注目されています。 社内規程や誓約書の見直し、研修実施まで一括支援し、「内部統制が形骸化しない」運用までをフォローします。
ポイント
✅ 「ChatGPT利用ガイドライン+誓約書」で漏えいリスクを低減
✅ 外部通報窓口の設置で問題を早期発見
✅ 上場企業監査役経験を活かした内部統制構築で取引先・株主からの信用も強化
【試用顧問プラン】の活用例
初めての内部統制見直しには、「1ヶ月トライアル顧問」で現行規程の診断の後、こちらの業務は外部専門家と共同で行うため、診断までは本プランの対応可能です。
退職社員の営業秘密漏洩防止、競業避止義務
取引先引き抜き・顧客情報流出を防ぐ仕組みづくり
退職後の「顧客リスト持ち出し」や即転職による競合リスクを最小化するため、秘密保持契約(NDA)、競業避止義務合意書の作成・運用を支援。内部告発など複合トラブルも含めて迅速に対応します。
【Q&A】4)退職社員の営業秘密漏洩防止・競業避止義務
Q: 退職した社員が、取引先の担当者に直接営業をかけているようです。顧客情報の流出や引き抜きを防ぐには、どう対応すれば良いでしょうか?
A: 本件は、 営業秘密の漏洩対策と競業避止義務の運用を「有効性のある形」で機能させる ことが重要です。
1. 現状の契約書・誓約書を点検する
まずは、当該社員との間に秘密保持契約(NDA)や競業避止義務に関する合意書が存在するかを確認します。 内容が抽象的すぎたり、退職後の制限期間・範囲が不明確な場合、裁判で無効になるリスクもあるため、見直しが必要です。
2. 取引先への通知と防衛策
取引先が、元社員の営業活動を受けている場合、自社の営業秘密に基づく勧誘行為であることを伝え、取引先に対して注意を促す書面を送付するケースもあります。 必要に応じて、弁護士名で内容証明郵便を送り、勧誘行為の差止めを求めます。
3. 訴訟・仮処分の検討
秘密情報の持ち出しや顧客引き抜きが明白な場合は、損害賠償請求や営業差止めの仮処分を検討します。 証拠として、メール履歴や退職前後の動きをしっかりと整理することが重要です。
4. 退職時の管理プロセスを強化
今後の再発防止のためには、退職手続きの際に秘密保持誓約書の再締結、PCやスマホのデータ削除、社内のアクセスログの保存など、実務フローを確立することが効果的です。
ポイント
✅ NDA(秘密保持契約)や競業避止義務は「条文の作り方」と「運用」が命
✅ 顧客引き抜き対策は、取引先への通知と法的手段をセットで考える
✅ 内部告発など複合トラブル化する前に、弁護士が第三者として介入するのがおすすめ
【試用顧問プラン】の活用例
退職社員との契約書レビューから、顧客リストの漏洩防止策まで、 1ヶ月トライアル顧問 で現状把握と対策プランをご提案できます。
債権回収・取引トラブル対応
滞納リスクの予防から回収・訴訟対応まで
売買契約・業務委託契約の作成、業種別のリスク診断を通じて取引トラブルを未然防止。万一の売掛金滞納には、内容証明送付・訴訟・強制執行まで一気通貫で支援し、与信管理体制の整備も可能です。
【Q&A】5)債権回収・取引トラブル対応
Q: 取引先の支払いが遅れがちで、何度も督促しても改善されません。回収の流れと予防策を教えてください。
A: 本件は、 「未然防止」と「いざという時の回収スキーム」をセットで備えておくこと が重要です。
1. 取引基本契約と個別契約での予防策
基本契約書に、支払期日、遅延損害金の条項を明記しておくと、遅延時の請求根拠が明確になります。 与信調査を徹底し、必要に応じて担保設定や保証人をつけることも大きな防御策です。 究極の対策は、契約書を公正証書にして、強制執行認諾文言を付けておくことです。これがあると裁判しなくても、強制執行できます。
2. 督促・内容証明の活用
期日までに支払われない場合は、速やかに内容証明郵便で支払いを正式に催告します。 これにより、法的措置の意思を示すことで、相手が応じやすくなります。
3. 分割払い・和解交渉も選択肢
相手に一括返済が困難な場合は、分割払いに応じつつ、債務承認書や和解契約書を公正証書化することで、強制執行が可能な形にしておきます。
4. 訴訟・強制執行
督促や交渉で解決しない場合は、訴訟を提起し、確定判決を得たうえで、相手の財産を差し押さえます。 基本契約書の他、取引履歴、請求書、督促状などの証拠を整理しておくことが肝要です。
5. 事後の与信管理体制の構築
債権回収をきっかけに、取引先管理の仕組みを見直すことが大切です。 顧問先の場合、契約書チェックから内容証明送付、訴訟対応までを一気通貫でサポートします。
ポイント
✅ 契約書の「遅延時の条件明記」「与信審査」が未然防止の鍵
✅ 督促〜訴訟までの流れを平時に整理しておく
✅ 顧問契約があれば、回収プロセスがスムーズに進みます
【試用顧問プラン】の活用例
初回ヒアリングで、取引先のリスク診断と、裁判が不要になる契約書作成も説明できます。1ヶ月で1社の債権回収リスク対策が可能となります。
会社法・各種業法対応(業種毎の予防策)
株主総会・取締役会・M&Aもスムーズに進める
同族経営からのガバナンス強化、取締役会改革、株主総会の適正運営に至るまで非上場企業でも安心の体制を構築。M&A・事業承継・特定商取引法など各種業法に応じた法務アドバイスで、経営リスクを最小化します。
【Q&A】6)会社法・各種業法対応(業種毎の予防策)
Q: 同族経営の会社ですが、事業拡大に伴い、取締役会改革や株主総会の運営をきちんと整えたいと考えています。また、業種ごとに注意すべき法律があれば教えてください。
A:会社は規模に応じた経営が必要です。会社が大きくなるとき、それに見合う態勢が必要です。面倒ですが、きちんと株主に関する業務を遂行していきましょう。
株主総会を円滑に開催するためには、法的な手続きや準備が必要です。非上場企業の場合でも、会社法に従って株主総会を開催し、必要な議案を処理することが求められます。
また、同族経営から従業員や取引先が株主となった場合は、ガバナンス体制の見直しや株主の関与を強化することが重要です。以下に、具体的な手順と留意点を詳しく説明します。
1.株主名簿の確認と整備
株主総会を開催する前に、まずは株主名簿を確認し、最新の株主構成を把握します。株式の譲渡や新たな株主の追加が適切に反映されているか確認します。特に、同族経営から株式を従業員や取引先に譲渡した場合、新しい株主が適切に登録されているかどうかが重要ですます。
株主の議決権の確認
株主総会では、各株主が議決権を行使します。議決権は保有株数に応じて割り当てられるため、株主名簿に基づいて、各株主の議決権を正確に把握することが必要です。
2. 株主総会の開催通知
株主総会を開催するためには、株主に対して総会の開催日程や議題を通知する必要があります。非上場企業であっても、会社法に基づき、総会の2週間前までに株主に対して書面で通知を送付するのが一般的です。通知には、議題の詳細、議案の内容、および議決権行使の方法が記載されていることが重要です。
株主の出席確認と委任状の準備
株主が総会に出席できない場合、委任状による議決権行使が認められます。出席できない株主からの委任状を事前に集め、議決権行使に問題がないよう準備しましょう。
3.総会の議題の設定と議案の準備
株主総会では、業績報告、取締役選任、役員報酬の決定、会社の方針などが主な議題となります。社長交代を行う場合、新社長の選任議案を含める必要があります。株主に対して、これらの議案を明確に説明できるよう、事前に資料を準備しましょう。
取締役の選任と報酬
同族経営から株式を一部従業員や取引先に保有させた場合、新たな株主が取締役の選任や報酬に関与する可能性があります。取締役の選任は、企業のガバナンスに直結する重要な議題です。株主が納得できる形での議論を行うことが必要です。
利益配当や株主還元策の検討
業績が拡大しているのであれば、株主への配当や還元策を検討することが株主の満足度向上につながります。利益配当の方針や計画を総会で報告し、株主の理解を得ることが大切です。
4.株主総会の進行と議事録作成
総会当日は、議長が円滑に議事を進行できるよう、議事進行の台本や資料を準備しておきましょう。議案については、簡潔かつ明確に説明し、株主の質問や意見に対応できる体制を整えます。
議事録の作成
総会終了後、議事録を作成し、法的に必要な保存期間に従って保管します。議事録には、総会での決議内容や議決権の行使状況などを正確に記録します。
特に、株主総会で決定された事項は、後日のトラブルを避けるためにも、書面として確実に残しておくことが重要です。
5.同族経営からのガバナンス体制の見直し
株式を一部従業員や取引先に譲渡した場合、これまでとは異なるガバナンス体制が求められます。新しい株主の意見を反映し、ガバナンスを強化するために、定期的な株主との対話や情報提供が必要です。
ガバナンスの透明性の確保
非上場企業であっても、ガバナンスの透明性を確保することは、企業の健全な成長に不可欠です。取締役会の定期開催や役員の責任明確化、業績報告の適切な開示などを通じて、透明性を高め、株主からの信頼を築きましょう。
6. 株式譲渡や取引先への配慮
株式を従業員や取引先に譲渡した場合、これまで以上に取引先や従業員との関係が密接になります。これらの新たな株主に対しては、適切な説明や配慮を行い、株主総会での意思決定に参加できるようにすることが重要です。
従業員株主には、会社の将来に関する意見を表明できる場を提供し、従業員のモチベーション向上にもつなげます。
非上場企業でも株主総会を適切に開催することは、企業ガバナンスを強化し、株主の信頼を得るために重要です。特に、株主構成が変わった場合や、業績拡大によるガバナンス強化が求められる場面では、事前の準備や議題の設定が成功の鍵となります。
当事務所では、株主総会の準備から進行、議事録作成、ガバナンス体制の見直しに至るまで、総合的な法務サポートを提供し、企業が健全な成長を遂げるためのお手伝いをいたします。
これら業務は、当法人と顧問契約を締結し、最初の年は株主総会開催1式着手金20万〜、成功報酬・登記20万〜で承りました。翌年からは総務の方に業務を覚えていただきました。
© 弁護士法人日新法律事務所